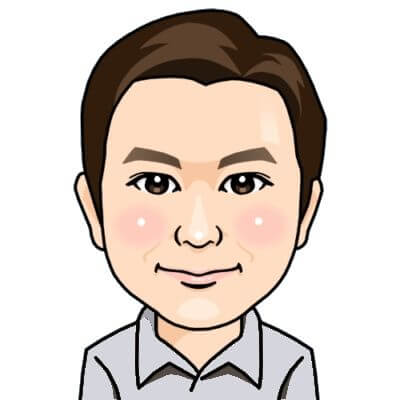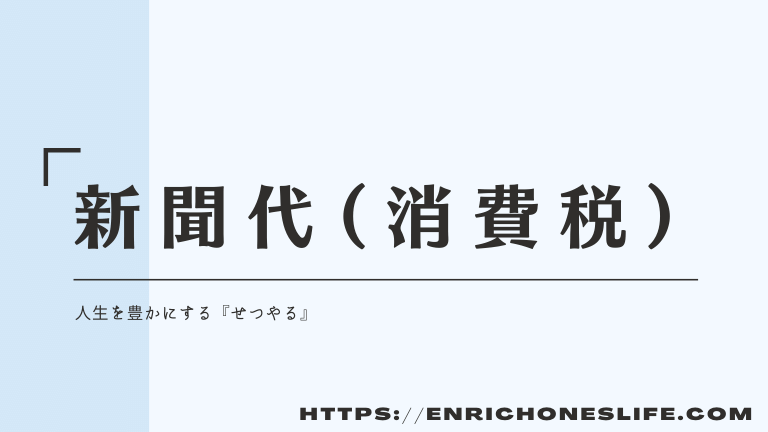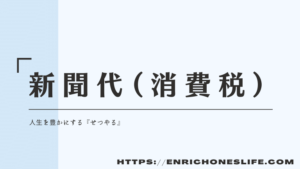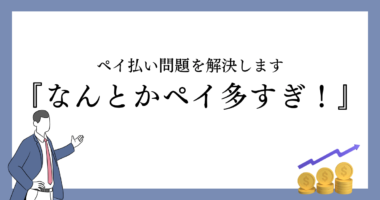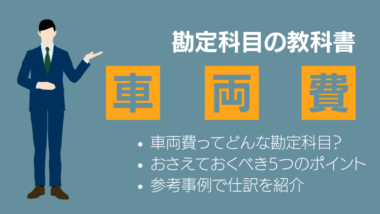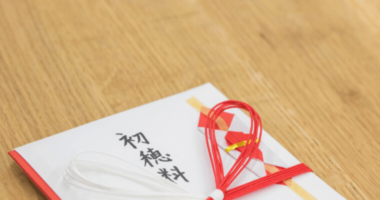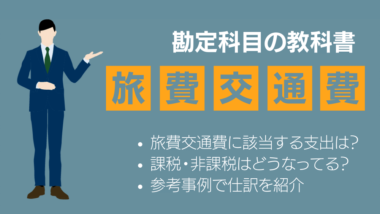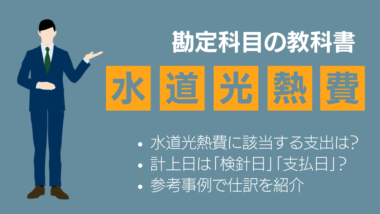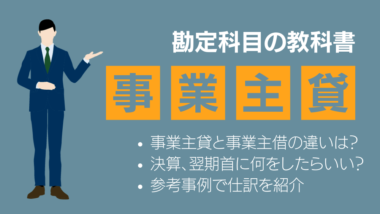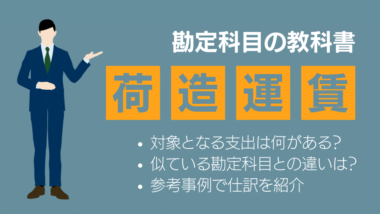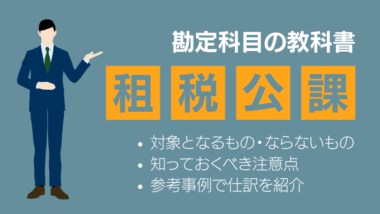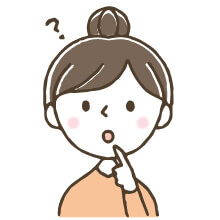
- 新聞代の消費税は何%?
- 新聞代は軽減税率?
- 軽減税率って何?
今回の記事では2019年10月1日以降の消費税の増税により新聞代にかかる消費税率がどう変わったのかを説明しています。
結論を言ってしまうと新聞代にかかる消費税は一定の条件を満たすと軽減税率(8%)の対象となります。
新聞代の消費税が軽減税率の対象となる場合には、どのような条件が必要なのかを理解しておく判断が余裕になります。
記事の前半で「軽減税率」について説明し、中半で「新聞が軽減税率の対象となる3条件」を説明しています。
また、記事の後半では「判断を迷いやすいパターン」を紹介しています。
最後まで読んでいただくと新聞代の消費税率について今後迷うことはなくなります。
消費税の軽減税率とは?

軽減税率とは、特定の商品の消費税の率(%)を低く設定することをいいます。
2019年10月1日から、消費税が10%と増税されましたが食料品や新聞などは低所得者対策として8%のまま据え置かれています。
この据え置かれた8%の税率が軽減税率です。
増税前と同じ8%の税率ですが中身は異なります。(税理士さん以外はあまり気にしなくてもよい情報です)
- 増税前:国税6.3% 地方税1.7%
- 増税後:国税6.24% 地方税1.76%
新聞代の消費税が軽減税率の対象となる3条件

消費者の経済的な負担を抑えるために設定されている新聞代の軽減税率ですが、次のような条件を満たす必要があります。
新聞代が軽減税率の対象となる3条件
- 定期購読契約で購入していること
- 週2回以上発行されていること
- 政治、経済、社会、文化等の一般社会的事実が掲載されていること
特に❶と❷の条件をもとに会計事務所では軽減税率の判定をしています。❸については、すこし抽象的な言い回しになっているので感覚的に判断材料としています。
新聞代が軽減税率の対象となる理由

そもそも、新聞代がなぜ軽減税率の対象となるのか?
食料品が軽減税率の対象となるのは理解できますが、新聞代が軽減税率の対象となるのはいまいち理解できませんよね。
日本新聞協会は以下のように答えています。
Q:なぜ新聞に軽減税率が必要なのか?
A:ニュースや知識を得るための負担を減らすためだ。新聞界は購読料金に対して軽減税率を求めている。読者の負担を軽くすることは、活字文化の維持、普及にとって不可欠だと考えている。
ヨーロッパでは、イギリス・デンマーク・ノルウェイなどのように新聞には一切消費税がかからない国もあります。
また、欧州連合(EU)加盟国でも多くの国において新聞が軽減税率の対象となっています。
その理由は「新聞は思索のための食料」といった考え方があるようです。
実際のところ、早い段階から国に対して新聞を軽減税率の対象となるように根回ししていたことが要因であるように思います。
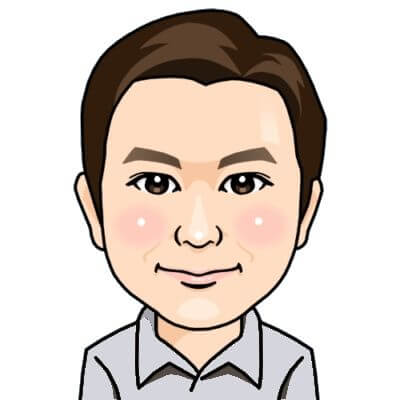
新聞代にかかる消費税が軽減税率の対象か判断が難しいパターン

スポーツ新聞
『政治、経済、社会、文化等の一般社会的事実が掲載されていること』の条件に当てはまるかどうかが微妙ですが、スポーツ新聞も軽減税率の対象となります。
ただし、定期購読していること、週2回以上発行されている必要があります。
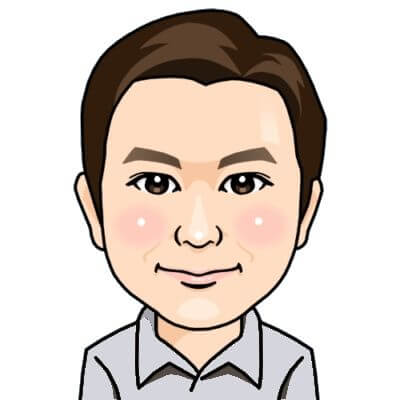
業界紙
こちらも『政治、経済、社会、文化等の一般社会的事実が掲載されていること』の条件に当てはまるかどうかが微妙ですが、業界紙も軽減税率の対象となります。
ただし、定期購読していること、週2回以上発行されている必要があります。
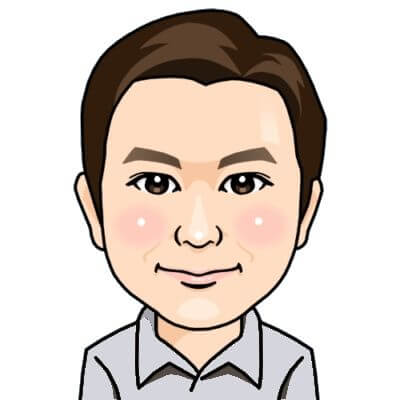
英字新聞
こちらも『政治、経済、社会、文化等の一般社会的事実が掲載されていること』の条件に当てはまるかどうかが微妙ですが、英字新聞も軽減税率の対象となります。
ただし、定期購読していること、週2回以上発行されている必要があります。
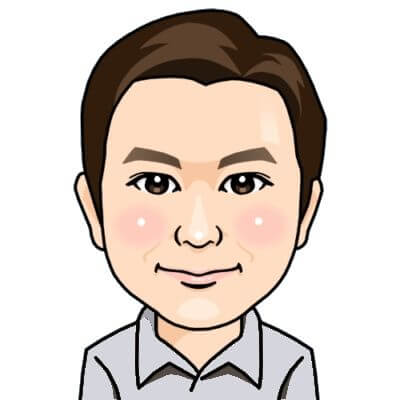
電子版の新聞

電子版の新聞は軽減税率の対象とはなりません。
軽減税率の対象となるには「新聞の譲渡」が行われることが必要であり、電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当し、現物の譲渡がないことから「新聞の譲渡」にはあてはまりません。
「新聞の譲渡」にあてはまらない=軽減税率の対象となりません
トンチみたいな感じでわかりにくいですが、電子版の新聞は10%と覚えておきましょう。
消費税の課税条件は以下の3つ
- 資産の譲渡
- 資産の貸付
- 役務の提供
コンビニや駅の売店で購入する新聞
定期購読の条件を満たさないため、コンビニや駅の売店で購入する新聞は軽減税率の対象ではありません。
つまりコンビニや駅の売店で購入する新聞は10%となってしまうので、もし毎日コンビニで購入しているなら定期購読契約をしましょう。
通常週2回発行の新聞が休刊日により1回しか発行されなかった新聞
休刊日などによって普段週に2回発行されている新聞が、1回しか発行されなかった場合も軽減税率の対象となります。
消費税は契約条件により判断するので、契約上週2回発行の新聞であれば問題ありません。
週一回の発行の時のみ10%になるようなこともないですよ。
住宅の賃貸などは通常非課税ですが、契約期間が1ヶ月未満だと課税になります。
この場合も実際に利用したのが15日のみであったとしても契約上1ヶ月以上となっていると非課税となります。
電子版と紙版のセット販売の場合
判断が難しいのが電子版と紙の媒体がセットとなっているような場合です。
上でも述べたように電子版は新聞の譲渡がないので軽減税率の対象とはなりません。
日本経済新聞の場合、日経Wプランといった宅配と電子版がセットとなった料金体系があります。
宅配4,000円+電子版1,000円
上記金額は税込価格で端数の出ないような設定金額になっていますが、実際には以下の消費税が含まれています。
宅配:4,000×8/108=296円
電子版:1,000×10/110=90円
税込価格から消費税額を計算する方法
- 軽減税率:税込価格×8/108
- 通常税率:税込価格×10/110
日経新聞を無料で読みたい方はこちらの記事もおすすめです。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://enrichoneslife.com/nikkeimuryou/ target=]
販売店・取扱店の取扱う新聞代の消費税率
ここからは新聞を販売している業者や新聞をサービスで提供している業者の取り扱いについて説明していきます。
新聞の販売店

新聞の販売店の仕入れについては、軽減税率の対象にはなりません。
理由としては、軽減税率の条件の「定期購読」に該当しないからです。
駅の売店やコンビニの場合は、仕入れも売上げも10%となるので負担はほとんどありませんが、
町の新聞販売店は個人の方との定期購読での契約となるため、売上げは軽減税率8%に対し、仕入れは10%となります。
消費税の納税額は、売上げに対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引いた残額を国に納付します。(実際にはもっと複雑ですが…)
100円(税抜)の新聞を仕入れて、100(税抜)円で売った場合
仕入れ:100円×10%=10円
売上げ:100円×8%=8円
納付額:8円-10円=-2円
※-2円となり仕入れに支払った税金が多くなりますが、2円については確定申告の際に還付(国から返金されること)されます。
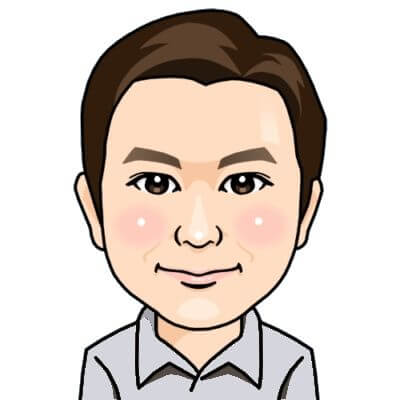
ホテルが購入する新聞

ホテルでは宿泊者に提供するため新聞を購入していますが、この場合の仕入れは軽減税率の対応になるのかを見ていきましょう。
この場合の新聞の購入は契約により決まった部数分については軽減税率の対象となります。上で紹介した3条件を全て満たすためです。
ただし、注意しなければならないのが追加で購入する部数分については軽減税率の対象外となります。つまり、10%の税率になってしまいます。
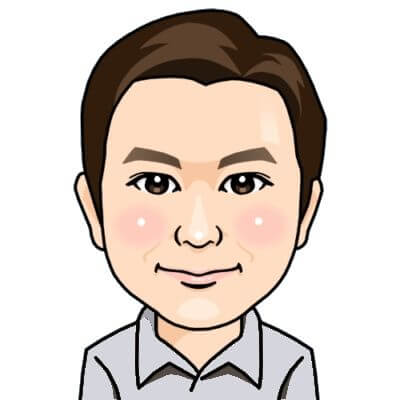
会社が購入する新聞
一般家庭ではなく会社が定期購読している新聞も、3条件を満たす場合には軽減税率の対象となります。
新聞以外の印刷物の消費税
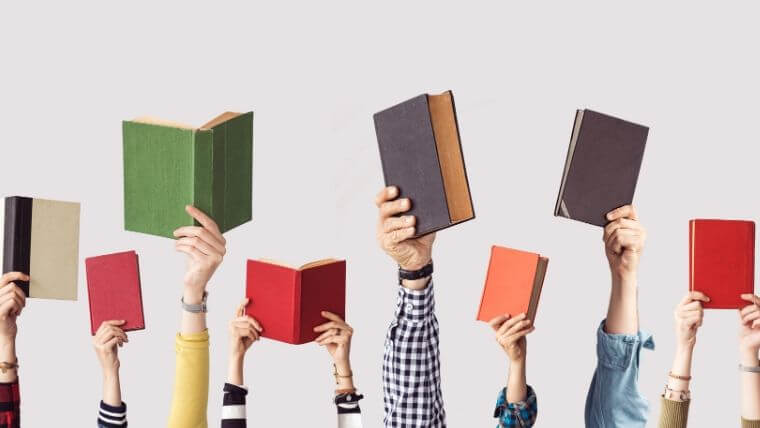
書籍や雑誌については、軽減税率の対象にはなりません。
ヨーロッパにおいては、新聞以外の書籍や雑誌についても軽減税率が採用されている国もありますが、日本では「有害図書」の取り扱いが不明確なため軽減税率の対象から外されました。
日本では有害図書(ポルノ雑誌)か否かの線引きが定まっていないため、一律に標準税率で対応することとなっています。
ヨーロッパの書籍に対する税率
- フランス:5.5%
- ドイツ:7%
- イギリス:0%
新聞代の消費税:まとめ

新聞代が軽減税率の対象となるには、以下の3条件を満たしている必要がある。
新聞代が軽減税率の対象となる3条件
- 定期購読契約で購入していること
- 週2回以上発行されていること
- 政治、経済、社会、文化等の一般社会的事実が掲載されていること
そして、もう一つ忘れていけないのが電子版の取扱い。
- 電子版は軽減税率の対象にはならない。
この3条件+αで新聞代の消費税はすべて判断できます。